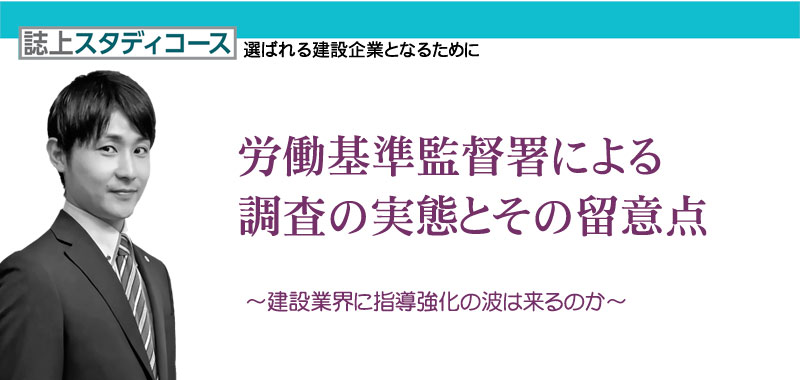はじめに
企業を経営する上では、様々な手続き・申請を行う機関とのやり取りが多く生じます。例えば法務局や税務署、年金事務所、ハローワークなどですが、これらの機関は手続きを受け付け・処理するだけではなく、定期・不定期に企業に対して「調査」を行っており、皆様もいずれかには該当したことがあるのではないでしょうか。今回取り上げるのは、そのうちの「労働基準監督署」(以下、労基署)による調査です。その特性と今の時代におけるリスクについて述べていきたいと思います。
労基署調査とはどのようなものか
労基署による調査は、対象企業における労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法といった労働関係法令における違反等の有無を確認し、その是正を企業に求めるものです。よってその調査事項は賃金、労働時間、安全衛生など多岐にわたりますが、そんな労基署調査を知る上で、まずは調査の種類やそこに至る経緯を知っておくことは非常に重要です。調査に至る経緯は大きく分けると三つあります。
一つめは「定期監督」と呼ばれる、各労基署において月10社程度をランダムに選出し実施する調査です。ただ実際のところは全くのランダムであったり、またすべての企業を順番に調査しているわけではないため、対象となる頻度は企業ごとに大きく異なります。労基署調査は、厚生労働省が策定する「監督指導計画」に基づいて実施されていますが、この計画は直近の行政課題を反映しているため、その要素に該当する企業が調査対象になりやすいといわれています。例えば、働き方改革が始まった2019年以降については、対策の主軸である「長時間労働」に焦点を当てた調査が多く実施されるようになりましたし、またそれ以外にも図1のような企業が調査対象として挙がりやすいといわれています。同様に考えると、2024年問題という労働時間に関連する大きな転換期を迎えた建設業界が、今後、調査の重点業界として位置づけられ、対象企業がこれまでよりも増加していく可能性は一定以上あるといえるでしょう。
二つめは労災事故を契機としたものです。建設現場等で事故が起こった際に、重傷や死亡など重大な災害であった場合、もしくは災害発生の原因が現場の安全管理上の問題に起因すると推察される場合などは、労基署は多くの場合で現場の安全衛生に焦点を当てた調査を実施しますが、それに伴って労働時間や賃金などといったその他の事項についても横断的に調査が行われることがあります。建設業はその特性から労災発生率も高く、また発生時には重大事故に発展する可能性も高い業界であることを鑑みると、事故をきっかけとして調査対象となることも比較的多い業種であるといえます。
三つめは「申告監督」とも呼ばれる、従業員が労基署に何らかの相談・申告を行ったことを端緒として行われる調査です。申告者が不利益な取り扱いを受けることなどを避けるため、申告者の氏名などは本人の了承がない限り労基署は公表しないことになっています。よって実際に調査が行われる際には、表向きは先に述べた定期監督と称して調査が行われるケースも多くなっています。
このタイプの調査の留意点としては、たとえそのきっかけが特定の従業員の特定の項目(残業代など)に関する相談だったとしても、多くの場合に調査対象は全従業員で、そしてあらゆる労務管理項目に及ぶため、その影響は企業全体に波及します。よって間接的な対策とはなりますが、従業員から不満や改善を求める声が聞こえてきた場合に、早期に可能な対応を行うことで円満な関係性を構築することは、当調査に対するリスクヘッジの観点からも重要だといえるのです。
労基署調査の対象となりやすいとされる企業傾向
・ 36協定(特別条項)に、80時間超など比較的長時間の上限時間設定をしている企業
・ 月80時間を超える時間外・休日労働が疑われる企業
・ 各都道府県労働局の行政運営方針で、その年に重点的に調査を行うと決められた業種
・ 定期的に労基署に届け出が必要な書類(36協定など)が、提出されていない企業
・離職率が高い企業
・従業員数が多い企業
・労災の発生頻度が高い企業
図1
調査の流れと留意点
労基署調査のおおまかな流れは、①事前通知・連絡、②調査実施、③是正勧告書等の交付、④是正報告書の提出、となります。
調査時に提出を求められることが多い資料一覧
① 就業規則等一式
② タイムカード等の勤怠記録
③ 賃金台帳等の賃金資料
④ 各種協定書(36協定など)
⑤ 労働条件通知書(雇用契約書)
⑥ 有給休暇管理簿
⑦ 衛生委員会の議事録等
⑧ 健康診断個人票
※ ②③は「直近1年分」など期間が指定されます
 |
①事前通知・連絡は一概にはいえませんが、定期監督の場合は事前に調査日時や準備書類、調査場所(会社か労基署など)が記載された書面が送られてくることが多くなっています。調査日時は数週間程度先の日付を指定されることが多いため準備期間は十分に確保できますし、指定された日時に都合がつかない場合は、事前に監督官に連絡することで調整も可能です。よって社会保険労務士と契約されている企業の場合は必要に応じてその旨連絡し、事前に提出書類等について相談、また必要があれば調査への同席も依頼すると良いでしょう。
一方で企業として対応に苦慮することが多いのが、いわゆるアポなしでの監督官の来訪です。ただこの場合でも当日に「これから(もしくは〇時頃に)伺います」と電話があるケースもあります。労災をきっかけとしたものや申告監督は、現場の安全管理不備や残業代の未払いなど具体的な法令違反の疑いがあった上での証拠固めとして実施される要素が強いものです。そのため、事前の通知による資料の改ざんや破棄などの証拠隠滅を防止し実態を把握するために、抜き打ちによる調査となる可能性が、定期監督よりも高いとされています。
②調査実施は会社や現場に訪問するケースにおいては、就業時間管理の実態や就業規則の社内周知状況等について、従業員に聞き取りが行われることがあります。そのため、企業の回答と実態に相違がある場合は虚偽を疑われることになってしまいかねないため、実態に即した回答を心がけましょう。
③是正勧告書等の交付は調査日当日にその場で監督官が作成し、交付されることが多くなっています。この際交付されるのは、法令違反が見つかった事項について記載した「是正勧告書」と、法令違反とまでは断定できないが改善すべき事項を記載した「指導票」です。また働き方改革以後は、長時間労働(過重労働)に関して、専用の指導書が交付されることが増えました。これらについては報告期限が併せて記載されますが、監督官が企業側の意見や要望を聞いてくれることもありますので、自社として現実的な期日設定を相談するようにしましょう。
④是正報告書の提出については多くの場合、調査時に監督官からそのための書式の案内がありますので、それに沿って作成するのが原則ですが、実際は必要な項目を満たしていれば独自書式でも構いません。よって実務的には受け取った紙媒体によらず、編集が容易なワードやエクセルなどでデータを作成した方が便利でしょう。
報告の内容についても定型文や決まったルールは基本ありません。是正勧告書等に記載された事項に対して、会社として実際にとった対応について整理して記載すれば足ります。なお、調査時の監督官の指摘になんらかの反論や申し開きしたいことがあった場合には、調査時(是正勧告書等が出される前)に行っている可能性が高いといえますが、その際には思い至らなかった、もしくは新たな関連資料が見つかって状況が変わった部分がある、などといったような場合には、それについても是正報告書に記載することが可能です。
事前対策がいかに重要か
 |
労基署調査は、その企業に潜在していた労務管理上のリスクを顕在化させるものです。リスクの対象や度合いは企業により異なりますが、重大となりやすいのはやはり賃金関連(最低賃金を下回っていないか、残業代の算出方法に誤りはないか、未払いの有無など)です。例えば調査の結果、残業代等になんらかの未払いが認められた場合は、その分を遡及して支払うことが是正勧告されます。この場合の遡及期間としては3カ月~6カ月程度が多いとされていますが、これが従業員全員分ですと、企業によっては相当な額の支払いが必要となるケースも少なくありません。労基署に対する労働者からの相談・申告事項として、やはり賃金関連は非常に多く、そうした側面からも潜在的なリスクは高いといえます。
賃金関連に限らず、労務管理上のリスクというのは、顕在化する前と後で、その度合いが大きく変化するものであり、また打てる対策も変化するものです。よって企業は、調査対象となる前に自社のリスクを検証し、その上で可能な改善を図っておくことが何よりのリスクヘッジとなります。自社の労務管理の適正化・改善の契機として、労基署調査対策を位置づけてみてはいかがでしょうか。
イラスト:ヒガシヨーコ |